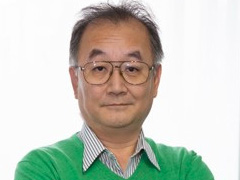ゲームデザイナー&研究者・遠藤雅伸インタビュー。
INDEX
解説――遠藤雅伸に聞く
デジタルゲーム産業はアメリカのアタリ社が発表した「PONG」(1972年発売)から始まるといわれている。
2017年、ついにゲーム産業は40年目を過ぎ、市場規模は日本・海外ともに拡大の一途をたどっている。それは業界内外で人材・コンテンツの競争が激しくなることを意味する。ゲーム開発にまつわる過去の資料やコンテンツをいかに利活用するか、それが個人・企業ともに生き残りのカギとなるであろう。
ではゲーム開発の資料をいかに保存・利活用するのか? その中でゲームの面白さはどう変化し、またプロのゲームデザイナーとなるにはどんな条件を満たせばいいのか?
今回お話をお伺いしたのは、日本のゲーム産業で活躍してきた遠藤雅伸氏。ゲーム「ゼビウス」(1983年)など数々のヒット作品を制作し、2012年に「遠藤雅伸のゲームデザイン実況中継」を執筆、現在は東京工芸大学でゲームデザインの教えるその人だ。
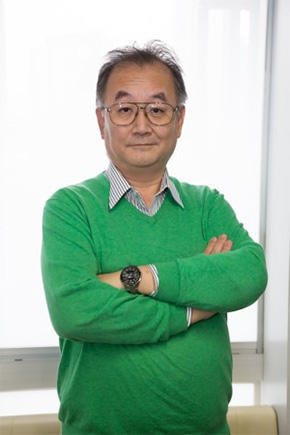
さらに注目すべきは、遠藤氏がゲーム研究・教育に積極的である点だ。
現在活躍されるプロの中には、学術団体「日本デジタルゲーム学会」(DiGRA Japan)の理事および研究発表大会「CEDEC」運営委員などを務める遠藤氏にお世話になった方々も少なくないだろう。その内幕にも光を当てている。
解説・質問は蔵原大(東京電機大学非常勤講師、アルテス=リベラレス開発研究所)ならびにゲーム産業に関わるD・S氏が務めた。なお記事中に「▼」として関連サイトを引用している。
ゲームアーカイブ(ゲーム資料のデータベース機関)の現代的意義
―― まず今手掛けておられる「あそぶ!ゲーム展1」「あそぶ!ゲーム展2」の意義をお教えいただけませんか。また遠藤先生のゲーム開発者としての名声は隠しようもありませんが、今回は研究者・学術者としての遠藤雅伸先生が何を目指しておられるのかもお聞きしたく思います。
遠藤 「あそぶ!ゲーム展」は基本的に企画展ですが、ゲーム系は企画展の方がいいですね。常設展にすると「いつか行けばいいや」と思われて結局来てもらえないからです。
なお「あそぶ!ゲーム展」はフェーズが分かれています。「1」は幻のゲームに触れられる・遊べるという趣旨。「2」はこれまで世の中に出てこなかったゲーム開発の資料を見せるところに力を入れています。
そもそも開発上の資料が日本のゲーム開発史の中でどんどん失われてきている。だから本来ならゲームの制作者が個人的に持っていた資料を、開発会社からオーケーいただいて公開する、それが正しいありさまだと考えています。
会社で資料を持っていてもいつか捨てられてしまう。そうならないためにも何らかの形で資料をデジタル化・公開する。そこに「2」の意義があります。

―― 先生の著書「遠藤雅伸のゲームデザイン講義実況中継」ではゲームアーカイブの重要性が指摘されています(同書「講義の終わりに」pp.360-363.)。「あそぶ!ゲーム展1」もまたアーカイブといっていいでしょうが、今後もゲームの資料やコンテンツを保存・公開する企画をお考えですか。
遠藤 自分で考える、企画するところまでは手がまわらないので、ゲームアーカイブの企画があったときにお手伝いするという姿勢でやっています。
なお僕が理事をしている「日本デジタルゲーム学会」(以下DiGRA Japan)ではアーカイブのタスクフォースを設けており、特にオーラルヒストリー(口述記録)系を重視しています。具体的には僕を含めてゲーム開発の黎明(れいめい)期を担った人たちがだんだんお亡くなりになっていく中で「ホントのことをお話してからお亡くなりになってほしい」という趣旨です。
この「ホントのこと」というのは、メディアやネットが育てた伝説に対し、当事者としての一次情報を残して欲しいということです。例えばゲーム「パックマン」の開発に際して「開発者はピザを食べたときにパックマンの形を考え付いた」という伝説がありますが、これはリップサービス的に後から付けられたものです。
本来は黄色という色がゲーム画面の中で一番大きく見える色であり、また丸い形が一番存在感を示せる形状ということ、従って「黄色い丸」が当時のビデオゲームにおいて最もプレゼンテーションを発揮するという論理的思考の結果です。
そういう形状のキャラに「食べる」という動作のアニメーションをさせると、それがたまたまピザに似ていた。という話をメディアが膨らまして「ピザから思い付いた」と言い出し、エピソードとして面白いので一般化し、もはや否定するのも大人げない状況になっているわけです。
僕の作品では「ゼビウス」はゲームを作る前にストーリーとなる小説を書いたという伝説がありますが、実際はできたゲームの設定を補完するために後から小説を書いています。このような伝説は一人歩きするので、事実である開発の事情をちゃんと話してから開発者の皆さんはお亡くなりになってほしい、という意味です。
同僚の岩谷徹先生(パックマン開発者、現・東京工芸大学教授)とは「そういう事情を話してから逝きましょう」と言い交わしている。逆に開発当時の事情が話されないままだと、「岩谷さんはピザを食べたときに……」といったメディアが捏造(ねつぞう)したウソが事実として残る恐れがあります。後世の研究者のためにも、信頼のおける一次情報で事実を残したい。そういう趣旨からDiGRA Japanでオーラルヒストリーが継続されています。
―― DiGRA Japanのアーカイブは、最終的には立命館大学の「ゲームアーカイブプロジェクト」やその他のアーカイブ組織と合体させるお考えはありますか?(※)
※立命館大学の「ゲームアーカイブプロジェクト」は文化庁の「平成24年度メディア芸術デジタルアーカイブ事業」に採択された。
遠藤 立命館の方は最終的にどうなるか分かりません。ですがアーカイブ自体がその主体に応じて変化してしまうことは既に分かっていて、行政にアーカイブさせると行政の方針が変わった瞬間に全部捨てられてしまう恐れがあります。
逆にいうとさまざまなコレクターが集めておられるコンテンツをリスト化するので十分かもしれない。そうなるとコレクターが亡くなったときの対処としてコンテンツの寄付先、受け皿を決めておく。その受け皿は公共的に機能するところが望ましいわけです。