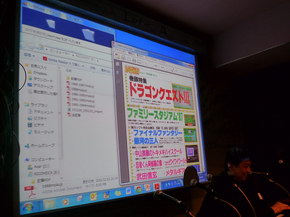「『忍者じゃじゃ丸くん』って書きながらオレは泣いちゃったよ」――あの人気雑誌の裏側を振り返るトークイベント「ヒッポン・エイジス」に参加してきた:日々是遊戯
平林久和氏や鈴木みそ氏など「ファミコン必勝本」関係者が昔を振り返るイベント「ヒッポン・エイジス」。平林氏が「じゃじゃ丸くん」で涙を見せた理由とは……。
あなたは「ヒッポン」を覚えていますか?
その昔、「ファミ通」「ファミマガ」「マル勝」と並んで、“4大ファミコン雑誌”と呼ばれた雑誌がありました。正式な名称は「ファミコン必勝本」。ファンには「ヒッポン」の愛称で親しまれ、他の3誌にはない自由な編集方針で、80年代のゲームカルチャーを先頭に立って牽引してきた雑誌のひとつです。
そんな「ヒッポン」に関わった編集者やライターたちが再び集まり、当時を振り返るトークイベント「ヒッポン・エイジス〜あの雑誌の誌面から振り返るテレビゲーム80's」が11月19日、阿佐ヶ谷ロフトAにて開催されました。出演者は、ゲームアナリストの平林久和氏をはじめ、漫画家の鈴木みそ氏、ライター・小説家のベニー松山氏などいずれも「ヒッポン」に関わり「ヒッポン」から巣立っていった現役の著名人たち。3時間にわたるイベントでは、貴重な「ヒッポン」制作の裏話も多数明かされ、ファンにとっては忘れられない一夜となりました。
「忍者じゃじゃ丸くん」で泣いた理由とは
個人的に印象深かったのは、創刊編集者のひとりである平林氏が、「ファミコン必勝本」創刊当時を振り返ったくだり。平林氏は当時コピーライターの仕事にあこがれて宝島社(当時はJICC出版局)に入社したものの、入社早々「ファミコン必勝本」の立ち上げ部署に配属され、大きな失望を感じていたそうです。
「当時はまだゲーム自体が世の中から低く見られていたし、メーカーへ挨拶に行くと部下が上司のことを“アニキ”と呼んでいたり、名刺を出そうとしたら相手の小指がなかったりとか、そういうことがしょっちゅうだった。ある時、会社で創刊のための資料を作ってたんだけど、『忍者じゃじゃ丸くん、ジャレコ』ってワープロに打ち込んでて、オレは泣いちゃったんだよ。この『じゃ』の韻の汚さ!(ここで会場は爆笑) 秋山晶に憧れて出版社に入ったのに、オレは何をやってるんだろうって」(平林氏)
当時のゲーム業界は「インテリが作ってヤクザが売る」とも言われていたほどで、そこに突然配属されてしまった平林氏が困惑するのも無理はなかったかもしれません。しかし、その後ある出来事がきっかけで平林氏は「ファミコン必勝本」の仕事に真剣に取り組むようになります。
「当時のゲーム業界なんて、100人いたら99人がろくでなしの集まりだった。でも、100人に一人、本当に天才だと思えるような人たちがいたんだよ。それこそ任天堂の宮本(茂)さんとか『ドラクエ』の堀井(雄二)さんとかね。そういう人に出会えたというのがひとつ。もうひとつは個人的な話になるんだけど、『ファミコン必勝本』が創刊されたとき、うちの父親が亡くなってるんです。それまでオレは父親からはいろんなことを教わってきたけど、これは父親からの最後のメッセージだと思った。オレは死ぬけど、同時にひとつの雑誌がこうして生まれた。おまえはそれに打ち込むべきだって。それでやっと、この業界とちゃんと向き合っていこうと思えるようになった」(平林氏)
平林氏はほかにも、当時のゲーム業界がいかにヤクザでバブリーだったかを物語るエピソードとして、こんな話も披露しています。会場では「オフレコで」とのことでしたが「タイトル名は伏せて」という条件付きで掲載許可をいただきました。
「あのころは出せば100万本と言われていた。当時『○○○○○○○』っていうとんでもないクソゲーがあったんだけど、それでも30万本売れた。それでメーカーの人が言ったんだって。『やっぱりこんなゲームじゃ30万本しか売れないよね』だって(笑)」(平林氏)
当時は「人買い」も日常的に行われていた!?
イベントの後半では、「ヒッポン」の略称が生まれるきっかけについて、当時読者コーナーを担当していた鈴木みそ氏が語る場面も。のちに「HIPPON SUPER!」へとリニューアルされ、愛称から正式名称になった「ヒッポン」ですが、そもそものはじまりは読者投稿だったそうです。
「読者からのハガキに『いい略称を考えました。ファミコン必勝本だからヒッポンでどうですか!』って書いてあって、面白かったからみんなに見せて回ったんだよ。『ヒッポンだって(笑)』って。そしたら半年後には誌名がヒッポンになってた(笑)」(鈴木みそ氏)
みそ氏はほかにも、当時の「ヒッポン」の制作風景を次のように振り返っています。
「とにかく人手が足りなかったから、仕事が終わった後に近所の朝までやってるゲームセンターに行って、若いヤツを物色するんだよね。俺は“人買い”って呼んでたけど(笑)。それで朝までゲームやってる不良をつかまえて、『ゲーム遊びながらお金がもらえる仕事があるんだけどどう?』って声をかける。そのまま会社に拉致して、『じゃあ写真撮れるまでやってね』っていうんだけど、そうすると大抵のやつは泣いちゃう(笑)。でもたまに泣かないヤツがいて、そういう一握りがものすごく使える」(鈴木みそ氏)
ゲームを売る方もヤクザなら、雑誌を作る方もなかなかのやんちゃぶり。しかし改めて振り返ってみると、そうした「危うさ」ともとれるような「やんちゃ」こそが、当時のゲーム業界の、そして「ファミコン必勝本」の魅力だったのかもしれません。
そうした当時の背景を象徴するものとして、ここでもうひとつ平林氏の言葉を紹介します。ベニー松山氏と、当時連載されていた「ウィザードリィ」の小説について振り返りながら、平林氏は次のように語りました。
「こうして振り返ってみると結局、オレたちはただやんちゃな80年代を送ってただけなんだよね。『ウィザードリィ』の小説にしたって、面白そうだから小説にしただけ。それが今じゃ、ベニー松山“先生”なんて呼ばれるようになった」(平林氏)
個人的には平林氏のこの言葉が、80年代と「ヒッポン」という文化をすべて言い表しているように感じました。当時はまだ未成熟で、しかしそれゆえに強烈な熱をもっていたゲーム業界と、そこをがむしゃらに駆け抜けていった「ヒッポン」。本来、悪い意味で使われることの方が多い「やんちゃ」という言葉こそが、今なお続く「ヒッポン」の人気を生み出し、支えてきたキーワードなのかもしれません。
終わってみればアッと言う間の3時間でしたが、最後に平林氏らが「またやりましょうか!」と次回開催に向け意欲を見せると、客席からはこの日一番の大きな拍手が。休刊から10年以上経ってもこうして愛され続ける「ヒッポン」の人気を改めて実感させられた一場面でした。今回参加できなかった人はぜひ、次回の開催を楽しみに待ちましょう。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
 日々是遊戯:メーカーはどこまでレビューに干渉できる? 誰も語らなかった「メーカーチェック」の表と裏とは
日々是遊戯:メーカーはどこまでレビューに干渉できる? 誰も語らなかった「メーカーチェック」の表と裏とは
ゲームの記事を載せる際、避けては通れないのが「メーカーチェック」。でもこれってホントに必要なの? 日々是遊戯:知る人ぞ知る名作「洞窟物語」がDSiウェアで配信決定! 作者自らが語る「洞窟物語のウラガワ」とは?
日々是遊戯:知る人ぞ知る名作「洞窟物語」がDSiウェアで配信決定! 作者自らが語る「洞窟物語のウラガワ」とは?
実は海外ではWiiウェアやニンテンドー3DS用ソフトにもなっている「洞窟物語」が、ようやく日本でも発売されます。もちろん3DSでもプレイ可能! 日々是遊戯:30時間で人はゲームを作れたのか!? 「福島GameJam」全作品を振り返る
日々是遊戯:30時間で人はゲームを作れたのか!? 「福島GameJam」全作品を振り返る
ゲーム業界だって被災地のために何かできるのでは――そんな思いから企画された「福島GameJam in 南相馬」。参加22チームによる力作、全26作品を一気に紹介します! 日々是遊戯:奇才・飯田和敏の次回作は「アナグラのうた」。プラットフォームはまさかの……
日々是遊戯:奇才・飯田和敏の次回作は「アナグラのうた」。プラットフォームはまさかの……
「巨人のドシン」や「ディシプリン」などで知られる飯田和敏氏が、日本科学未来館の展示プロジェクトに関わっていることが判明。その内容とは……? 日々是遊戯:あれあれ、人の頭上に体力バーが見えるぞ――あなたは「ゲーム・トランスファー現象」を体験したことがありますか?
日々是遊戯:あれあれ、人の頭上に体力バーが見えるぞ――あなたは「ゲーム・トランスファー現象」を体験したことがありますか?
「人々の頭上に体力バーが見える」、「コントローラのボタンを反射的に押そうとしてしまう」など、ゲームの体験を現実世界に持ち込んでしまう現象について、興味深い調査結果が得られたとのことです。 日々是遊戯:「パックマン」「スペースインベーダー」の生みの親が明かす、ビデオゲーム黎明期の真実
日々是遊戯:「パックマン」「スペースインベーダー」の生みの親が明かす、ビデオゲーム黎明期の真実
12月18日、19日に開催された日本デジタルゲーム学会の2010年次大会。初日の18日には、遠藤雅伸氏がモデレータを務める基調講演「日本ビデオゲームの黎明」が人気を集めました。- 日々是遊戯過去記事一覧