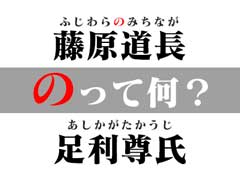「の」って何? という疑問をまるっと解決。
日本史の古い時代の人の名前には、「藤原道長(ふじわら“の”みちなが)」や「源頼朝(みなもと“の”よりとも)」など、名字と名前の間に「の」が挟まるものが出てきます。鎌倉時代以前の人の名前に特に多いですね。
しかし、時代を追って室町以降になると、「足利尊氏(あしかがたかうじ)」「徳川家康(とくがわいえやす)」など、急に「の」を挟まなくなっていきます。
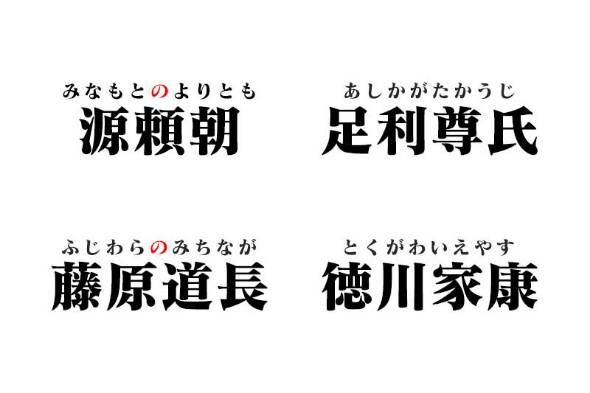
なぜ「源頼朝」には「の」がついて、「足利尊氏」には「の」がつかないのか。
それは、どちらもただの名字のような「源」と「足利」が、実はまったく別の性質のものだからです。
源頼朝の「源」は氏名(うじめい)
時代をさかのぼって説明します。
日本史で「名字+個人名」のように思われる形で最初に目につくのは、飛鳥時代の「蘇我馬子(そがのうまこ)」や「物部守屋(もののべのもりや)」でしょう。
この「蘇我」や「物部」は、祖先を同じくする人々の集まりである「氏集団(うじしゅうだん)」の名前で、「氏名(うじめい)」と呼ばれます。
ちなみに、蘇我は地名に、物部は朝廷で受け持っていた官職に由来する氏名です。日本でよく見る「服部」も、「はたおりべ」という官職からこの時代に生まれたとされています。詳しくは以下の記事をご覧ください。
さて、奈良時代に入っていくと、蘇我や物部といった古くからの氏集団の多くが権威を失うとともに、これから説明する新たな氏名が誕生します。
669年、大化の改新などに功があった中臣鎌足(なかとみのかまたり)に対して、天智天皇は新たな氏名である「藤原」を授けました。これが「藤原氏」のはじまりです。以降も、手柄を立てた人物などに対して、天皇から氏名が授けられることがありました。
天皇から賜ったうちの、源氏・平氏・藤原氏・橘氏の四氏は平安時代に特に繁栄し、よく「源平藤橘(げんぺいとうきつ)」ともまとめられます。源頼朝などの「源」も氏名なのです。
こうした「源」や「藤原」といった氏名には、慣例的に格助詞の「の」をつけて読んでいます。
「名字」の起こり
「源」や「藤原」が氏名(うじめい)であったことがお分かりいただけたと思いますが、では「足利」や「徳川」は氏名ではないのでしょうか?