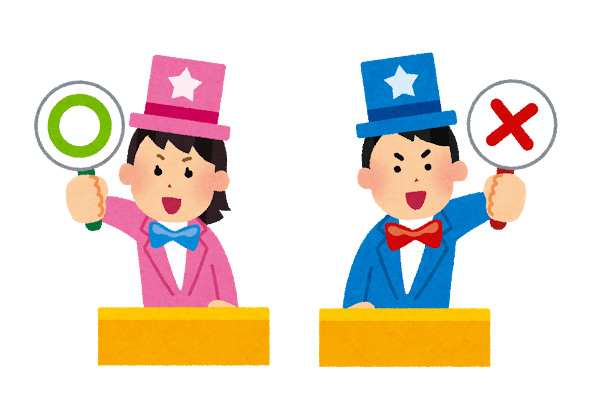クイズ大会を盛り上げるためのチェックリスト
- 必ず一問目は全員が正解できる問題にする
- チームは少人数単位で!
- 問題をゾーニングする
- 参加者全員が分かる言葉で問題を書く
- その団体の外で得た知識は半分以下に!
さて、前項を踏まえて、よりクオリティーを高くし、全員を満足させるためのチェックリストをクイズ王なりに作ってみました。これを全て満たせば、偏差値60くらいの余興が生まれるのではないでしょうか。あくまで余興ですが。
順に解説していきましょう。
まずは「一問目は全員正解」ルール。これは意外と大事です。周りが正解を重ねている中で、正解ゼロのチームがあると結構へこむもの。たとえその後点差が開こうと、一問正解しているだけで会話の弾み方は全然違います、間違いなく。飲み会でも最初の一杯はとりあえず乾杯するように、まずは正解してもらい、喜ぶ過程で会話してもらいましょう。
次に、「チームは少人数」で。先ほども言いましたが、大勢だとチーム内で議論に入れないひとが出てきます。2人から4人程度をひとまとまりにすれば、メンバーの名前も簡単に覚えられるし、全員が会話に参加できるはずです。
チーム数が増えて得点を管理するのが大変……みたいな部分は、各自にセルフでやってもらいましょう。そこでズルする意味もないですし。
お次は「問題のゾーニング」。何が言いたいかというと、「似ている問題はまとめる」ほうがよい、ということです。特に内輪ネタ問題など、分からない人に伝わらない問題はまばらに出されるとその都度なえてしまいます。3問なら3問で事前に伝えておくと、「ああもう終わる……」と切り替えることができますし、他の常識問題などでも同じことがいえます。逆に、「課長常識っぽいの苦手じゃないスカ?」みたいなイジりなど、得意苦手がハッキリ分かるがゆえの笑いを生むこともできます。
上に挙げた3つはどれもテクニカルな話ですが、技術以上に大事なのが「作り手の思いやり」。中でも、全員が分かる言葉で問題を書くということは何よりも大事です。内輪ネタにしても「問題の意味が理解できない」ということにならないよう最低限の配慮が欲しいです。クイズへの参加は「考える」ことができれば達成されますが、問題の意味が分からないと考えることすらできないからです。なるべく優しい言葉で、分かりやすく文を書きましょう。
最後の「その団体の外で得た知識は半分以下に」も思いやり条項ですね。知ってる人と知らない人が生まれる問題は、パーソナルな内容や共通の仕事に関してのものならまだネタにできますが、そうでないものだと厄介です。
もちろん差をつけるためにはそういう問題が必要ですが、常識問題などで差がつきすぎると明確な優劣が生まれ、せっかくの楽しい会話に水を差します。そのような問題を出して差がつくのはしょうがないので、絶対量を減らすことで気持ちを抑えておきましょう。
以上、より良い企画を作るためのプラスワン条項でした。企画を考えているときというのはとにかくてんてこ舞いで、細かいことに頭がまわらないものです。このあたりのことに気を付ければ、100点満点で75点以上は確実なように思います。
困ったらこれをパクれ! 想定クイズ大会
ではいよいよ、クイズ王的「こんな余興なら余も満足じゃ」企画を発表します。3人くらいのチーム編成を想定しています。ぜひ、おいしいところだけパクってみてください。
- 会話を呼ぶ! ジェスチャークイズ
- 鉄板は世代トーク 世代格差クイズ
- やはり王道の○×クイズ
まずこれは間違いない、というのが「ジェスチャークイズ」。出されたお題を一人が体で表現し、のこり2人が当てる、という形式のものです。得点が倍になる難問お題を入れてもいいかもしれません。このクイズの良いところは、事前の能力がほとんど関係ないところと、それゆえにみんな一生懸命になれるところです。チームのアイスブレイクとしては最適かと思います。
次にオススメするのが、最近テレビでも人気の「世代格差クイズ」。アイドルといえば、スポーツ選手といえば……というジャンルごとに、それぞれの世代向けの問題を1問ずつ出していく。3択でも、フリップに書かせても良いと思います。特に幅広い年代の人が参加する場では、上下の垣根を超えたコミュニケーションにつながるはず!
ここまで2つはクイズの内容についてオススメしてきましたが、次はイチオシの「形式」です。ズバリ、クイズ王的に一番盛り上がる形式は「○×クイズ」です。
どんな題材も料理しやすく、書籍やネットなどにも大量の問題が載っていてパクりやすい。話し合いもしやすいし、判定も非常に分かりやすいという、いいことづくめの形式です。テンポも良いので、全部○×でもサラッと企画が成り立ちます。○×だけなら、個人戦にしても成り立つくらいです。
今まで数多のクイズ大会やイベントに出場してきましたが、○×ほど皆そろって盛り上がることのできる形式はありません。それは、何人参加してもOKであり、かつ会話の余地が多分にあることによるものだと僕は思います。「高校生クイズ」などで使われ続けるゆえんですね。
ガチンコ感も出て、その上で一番大事な会話が生まれる。単純ですが、○×クイズを専門家の視点から強く強く推します。
まとめ
さて、上からつらつらと述べてきましたが、つまるところ余興のクイズ大会のつまらなさは「思いやりのなさ」に端を発します。チームにされたのになじむきっかけがない、知らない内輪ネタが多いなどの余興あるあるは、作り手側が思いやりを持てば解決すること。
僕がクイズを始めたころ、先輩方から「問題を作るときは、答える人がなるべく正解できるように作れ」と口を酸っぱくしていわれました。たとえ余興でも、答える相手のことを思いやって作れば、大失敗することはないはずです!
- 連載:クイズ王イザワの「分からないこともあります」記事一覧
関連記事
 「クイズ王」はクイズ王になる前には何者であったのか?
「クイズ王」はクイズ王になる前には何者であったのか?
さえない1人の中学生が、世間から「クイズ王」と呼ばれるようになるまで。 スマホってどれだけ進化したの? 2017年に「iPhone 3GS」で生活してみた
スマホってどれだけ進化したの? 2017年に「iPhone 3GS」で生活してみた
果たしてまともに動くのか……? 「カニミソ」はカニの何なのか?
「カニミソ」はカニの何なのか?
カニミソって何だ? 脳ミソか? 僕は何を食べようとしているのだ? なぜWordのデフォルトフォントサイズは「10.5」なのか?
なぜWordのデフォルトフォントサイズは「10.5」なのか?
「ルビ」の謎についても解説。 どこが違うの? 「サイダーとソーダ」「そうめんとひやむぎ」「アイスクリームとアイスミルク」
どこが違うの? 「サイダーとソーダ」「そうめんとひやむぎ」「アイスクリームとアイスミルク」
知ってるとドヤれる。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.