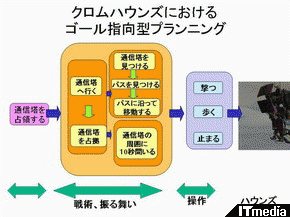大学からゲームメーカーへ――AI研究で広がるステキなゲームの世界とは?(前編):ゲームとアカデミーの素敵なカンケイ(第2回)(3/3 ページ)
「ゲームと学術界の素敵なカンケイ」第2回は、学界からゲーム業界に飛びこみ「ゲームAIの研究と実用」を志すフロム・ソフトウェアの三宅陽一郎氏をフォーカス。前編をお届けします。
日本で「デジタルゲームAI」を普及させるために何をしているのか?
―― 現状、日本と海外特にアメリカとの技術的な差が広がりつつあるわけですが、そこはどういうアプローチで埋めていくべきなのでしょうか。
三宅 現状、日本とアメリカの差がかなり広がっているのが現実です。その差があるおかげで、米のデジタルゲームAI技術を学ぶための敷居がものすごく高くなってしまっています。私がやるべきことの一つは、まずその敷居をなるべく低くすることです。例えば、IGDA JAPAN(国際ゲーム開発者協会 日本支部)では、ゲームAI連続セミナーを1年間に渡って全6回を開催しました。1回のセミナーについて、50から60の英語の論文を読んでギュッと圧縮してまとめたものを、80〜100名の企画とプログラマーに向けて解説していました。2007年に開催されたCEDECにおける講演でも、それらをまとめたものを解説しました。そして、そこから、海外の文献にリーチできるようにしように、資料へのリンクもリストしてあります。それ以降も、さまざまな講演や、CEDEC2008のAI day (デジタルゲームAIの一日連続講演)を開催するなどして、開発者が簡単に海外の文献やそこから自分で考えたことをゲーム開発に生かせるような情報環境の整備を続けています。
デジタルゲームAIに関する日本の文献が本当に少ないので、まずは日本の文献をなるべく増やして開発者の人に入り口を作ろうとしています。「そこから各論は英語の文献を読んでね」というつもりなので、現状はそういった方が少しずつ出て来てゲーム開発に活かせてくれているのは嬉しい限りです。結局、文献というのは、一つ日本語で押さえても、その参考文献を辿って行くと、英語圏の文献ネットワークに入ってしまうので、そういったネットワーク状に広がった文献を自分で解釈して進んで行く力が必要になります。それは、日本語の文献がいくら増えても変わりません。
―― 他にも、社内向けのセミナーを毎週やられているとか。
三宅 そろそろ130回目を数えるころでしょうか。入社してちょっとしてから始めました。週1回1時間のセミナーを社内向けにやっています。毎回、ゲームAIに関係する技術トピックを決めて、技術解説と、それを題材に如何にゲーム開発へ生かすための議論をしています。内容は難しいときはあっても、キーワードを設定して、毎回、言葉を一つだけでも覚えて帰ってもらっています。これが2回や3回なら、それほどの差はありませんが、20回、50回、100回と積み上げると、そもそも、ゲームAIを議論する語彙のレベルの差が全く違って来ます。このセミナーに出る人は、次第に自然にゲームAIについてレベルの高い議論が出来るようになるのです。それは、開発の現場でも大きな力になるのです。
―― ゲーム企業に限らず、一般企業でもこういったセミナーを行うのはレアなケースですね。
三宅 社内セミナーは、どの分野どの企業もそうだと思いますが、やろうとするとたくさんの圧力があります。もちろんこれは、業務時間を使うわけですから、会社の理解がないとこういったことはなかなかできません。また、何より、会社の中で成果を出すことが必要となります。そして、そのためには時間が必要です。なので、そういったことも周囲に理解してもらう必要があります。特に、ゲームAIのチャンスというものは、ゲームデザインに拠るところが非常に大きいので、少ないチャンスに備えて、機会が来たときに十分に対処できるようにしておくことが大切です。ゲームAI連続セミナーを通じて、最近、色々な会社でAIに限らず、セミナーを始めようという運きが徐々に始まっています。また、会社に一端根付いた文化というものは、必ずゲームタイトルに反映されます。もう一つの目標は、デジタルゲームAIの技術というものがあたり前になるぐらいに、会社に浸透させたいということがあるのです。そうすれば、高度なゲームAI技術でも、当たり前に、タイトルに反映できる時代が来るかもしれません。
―― 会社側が技術の格差に気がつき始めたということですか?
三宅 会社もそうですが、現場の開発者が「これはそろそろまずいんじゃないか」ということに気付き出した、ということです。自分の作っているゲームと、ニュースサイトで見るゲームやプレイしたゲームの差を開発者はいち早く敏感に察知します。高度なCG技術が急速にゲーム業界に浸透したのも、CGでは、その差が歴然として分かるからです。しかし、AIに関しても、そういった方向へ加速されつつあります。もちろん、ゲームAIは多様な方向があるので一概に比較することは出来ないのですが、AIに関して言えば日本はアメリカに7〜8年遅れています。この8年で米では、デジタルゲームAIに関する書籍、文献、論文の数を飛躍的に充実させて来ました。残念ながら、日本ではほとんどありませんでした。だから、日本ではその積み重なってきた海外のゲームAIの歴史に対して「どう理解して、どこから手をつけるべきなのか」を考えるところから始めなければなりませんでした。一つの文化が長い間欠落するとは、恐ろしいことです。語弊のないように言いたいのですが、日本にゲームAIがなかった、というのではなくて、アメリカのような意味でのゲームAIは発展しなかったというのが正しいかと思います。
もう一つ、見逃してはならないのは、欧米と日本の開発体制の違いです。欧米の開発体制では、レベルデザイナーが、自分の担当するステージの設計からAIまで、ゲーム性に責任を持つ担当者がいます。技術者は、そういったコンテンツ製作者に向けて、様々なツールを作成します。つまり、ツールによって、技術とコンテンツ製作が繋がれると同時に、役割が分離されます。しかし、ツールに技術を組み込むことで、技術導入がし易くなるという側面もあります。Haloでは、AI用のツールについてGDCで発表されていますが、GUIを用いてレベルデザイナーがAIやチームの特性を自由にカスタマイズできる環境が提供されています。
一方、日本のゲーム体制は、多くの場合に、コンテンツ至上主義で、極論すれば、企画がプログラマーの後ろにいて「ああして欲しい、こうして欲しい」と言いながら開発するか、あるいは「企画がスクリプトを書く」という体制が主でした。必要な場合に、必要に応じて、全てのAIの処理を書くという体制ゆえに、AIの作成は開発を進めながら必要に応じて作って行くものだという姿勢が出来てしまいました。もちろん、そういった開発体制が良い場合もありますが、少なくとも、今世代のラージスケールのマップ、ロングタイムのゲーム性の中では、そぐわなくなってきています。たとえるならば大きなキャンバスに、細い筆で点描して行くようなものです。これは、AIに限ったことでなく、全ての開発領域で言えることですね。
今世代の開発の体制を作るにあたって、各企業が行ったことは、コンテンツを製作する効率的なパイプラインを作ることでした。ところが、ここでも、AIというのはゲームデザインに依存するために、一概にパイプラインに組み込むことが出来ない難しさを持つのです。AIに関しては少なくともゲームごとに新しく調整しながらパイプラインの中へ組み込んで行くことが必要です。欧米ではプロトタイプを作る期間にこれが行われる場合が多く、それがツールという形で結実します。AIに関しては、実はこのプロトタイプの期間にいかにパイプラインの中に入り込めるかが導入の分岐点となります。
日本の企業にとって、プロトタイプの短い期間に、自身の持つコンテンツパイプラインへ向けて、デジタルゲームAIをいかに体系的に組み込めるかが、一つの飛躍の鍵となるのです。AIはコンテンツの一部ですから、コンテンツの質にそのまま影響します。必要なことは、常に基礎研究を継続しながらそういった少ないチャンスをものにしていくことです。
三宅氏オススメのAI資料は
- 「実例で学ぶゲームAIプログラミング」(オライリー・ジャパン、Mat Buckland著、松田晃一訳)
- Haloの公開開発資料
- John Ahlquist,Jeannie Novak, "Game Development Essentials: Game Artificial Intelligence" ,Delmar Pub.
三宅氏の資料はこちらで読めます
- y_miyakeのゲームAI千夜一夜(AI情報についてブログ)
- デジタルゲームAI講演資料
- エージェント・アーキテクチャから作るゲームAI(このCEDEC2007の講演資料が入門にはお薦めとのこと)
- 財団法人デジタルコンテンツ協会 デジタルコンテンツ制作の先端技術応用に関する調査研究報告書(第三章にゲームAI分野紹介がある)
- 日本デジタルゲーム学会「Spore におけるゲームAI技術とプロシージャル」(日常系AIの解説がある)
- AOGC2007 人工知能が拓くオンラインゲームの可能性講演資料(ページ下部に資料がアップされている)
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
 ゲームとアカデミーの素敵なカンケイ(第1回)――東京大学 大学院情報学環 馬場章教授
ゲームとアカデミーの素敵なカンケイ(第1回)――東京大学 大学院情報学環 馬場章教授
「ゲームとアカデミーの素敵なカンケイ」は、ゲームを学術的に研究するさまざまな人たちにフォーカスして、その研究内容や将来の構想についてうかがっていく。第1回目は、日本デジタルゲーム学会会長でありCESAの理事をつとめる、東京大学 大学院情報学環教授の馬場章先生。日本の最高学府では、どんな研究が行われているのか……?