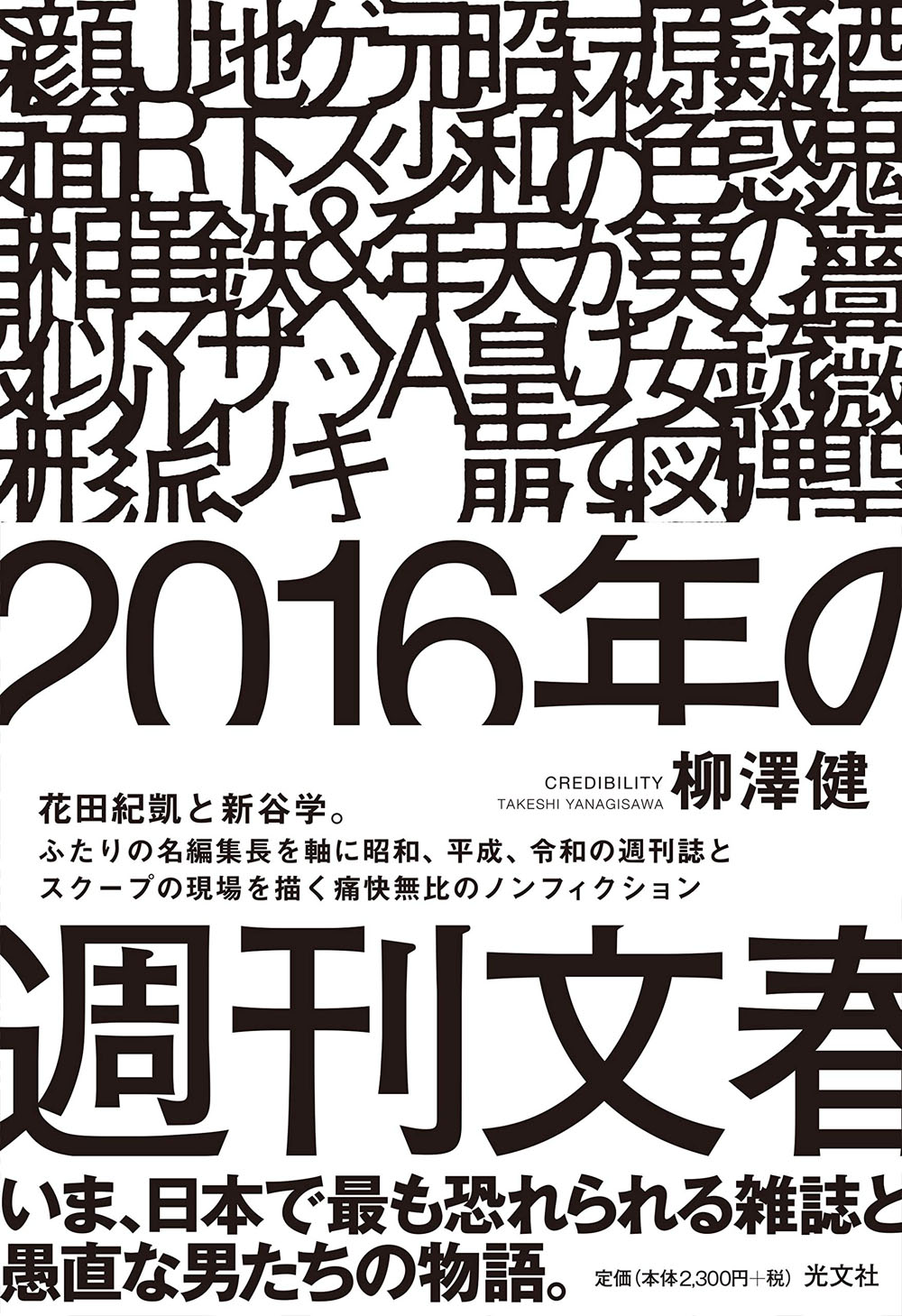ブログ「水平思考」のhamatsuさんによる不定期コラム。今回は書籍『2016年の週刊文春』を紹介。
現在、最も日本を騒がせているメディアと言えば、『週刊文春』だろう。毎週のようスクープを報じ続け、ネット全盛の現代にもかかわらず、紙媒体として気を吐き続けるこの雑誌の創刊から現在に至るまでの軌跡を追った著作が出版された。それが、今回紹介する書籍、『2016年の週刊文春』である。
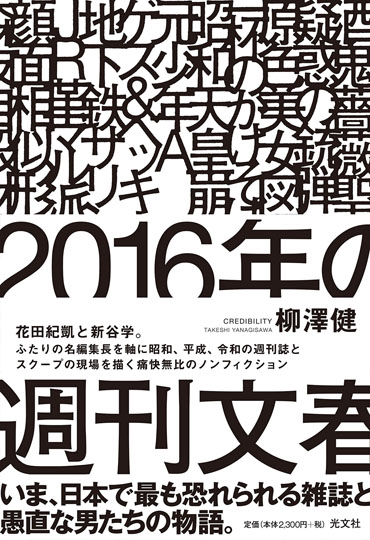
花田紀凱と新谷学という二人の週刊文春編集長を軸に、昭和、平成、令和という時代を駆け抜け続ける『週刊文春』の軌跡を鮮やかに描く『2016年の週刊文春』は出版や雑誌という枠組みを超えて、さまざまな「メディア」に関わる人全員にオススメしたい一冊となっている。
なぜ「週刊文春」は強いのか、なぜ「文春砲」の異名を得るに至るほどに世間に風穴を開けるほどのスクープを連発できるのか。この本を通してその秘訣(ひけつ)について考えてみよう。
ライター:hamatsu

某ゲーム会社勤務のゲーム開発者。ブログ「枯れた知識の水平思考」「色々水平思考」の執筆者。 ゲームというメディアにしかなしえない「面白さ」について日々考えてます。
Twitter:@hamatsu
時代を切り取る名手、柳澤健
この本の著者である柳澤健は、『1976年のアントニオ猪木』や『1985年のクラッシュギャルズ』『1984年のUWF』といったプロレス系の著作で有名な人物である。『1974年のサマークリスマス 林美雄とパックインミュージックの時代』のようなプロレスや格闘技とはほぼ無関係な著作もあるものの、主にプロレスや格闘技系の書き手だと思っている方が多いかもしれない。

しかし、柳澤健が一貫して主題としているのは「メディア」である。彼がアントニオ猪木や女子プロレスやUWFについて書くのはそれらの人物や団体が、人間の生き方を変えてしまうほどの強力な影響力を持った「メディア」として機能し、それがもっとも時代や状況との緊迫した関係を切り結ぶなかで輝く瞬間、時代が変わる特異点を捉えようとしているからだ。
だから彼の著作は『1976年のアントニオ猪木』や『1984年のUWF』『2000年の桜庭和志』といった形で、全て主題とする名前や団体名と共に“○○年”という時代の表記がなされるのである。アントニオ猪木が、現役のボクシングヘビー級チャンピオン、モハメド・アリと戦った1976年。新日本プロレスを抜けたメンバーで結成された新しいプロレス団体、UWFが旗揚げした1984年。桜庭和志が東京ドームにて、90分に渡る激闘の末、ホイス・グレイシーを打ち破った2000年。これら歴史的な出来事が起きる、決定的な瞬間を基点とし、そこに至る経緯とその後のいきさつを描くこれらの著作は、プロレスや格闘技といった分野に興味がある人以上に、題材となった人物、団体とそれらを生み出した時代状況、そしてその時代に人々が何に心を動かされ、何に熱狂したのかを考えたい人ならば、いずれも強くお薦めできる、読み応え抜群の名著ばかりだ。
そんな著者の最新作が『2016年の週刊文春』である。雑誌という「メディア」そのものを主題として選択し、さらに「週刊文春」を発行元である文藝春秋社は、柳澤健自身がかつて勤めていた会社でもある。つまりは著者自身が当事者であり、そのインサイダーとしての視点すら加わるというのだから、これは著者渾身の一冊が出たと思って間違いないだろう。
「週刊文春」の過去、現在、そして未来
というわけで『2016年の週刊文春』について紹介していきたいのだが、あらためてこの本を紹介しようとするとき、困ったことが一つある。それは、この『2016年の週刊文春』というタイトルがある意味では邪魔に感じられてしまうということだ。
なぜならこの本は、スクープを連発し、「文春砲」の異名を決定づけた2016年をクライマックスに持ってきつつも、それに至るまでの100年近い歴史を持つ文藝春秋社の成り立ちや『週刊文春』の誕生、ライバルである『週刊新潮』を発行部数で追い越すまでの軌跡、新谷学と並ぶ、本書のもう一人の主人公である花田紀凱の栄光と転落、スポーツ雑誌、『Number』の創刊時の逸話などにまで触れている。『2016年の週刊文春』というタイトルによって、2016年というたった1年にこの本の印象を集約してしまうにはあまりに内容が盛りだくさんすぎるのだ。
そしてさらに、本書の最終章は「文春オンライン」なのである。
そう、PV数など具体的な数値を軸に語られるこの最終章によって、本書はかつての雑誌の輝かしい黄金時代を振り返るだけにはとどまらず、2021年現在のメディア状況に接続される。
ついこの間のことのようにも思える2016年ですら既に5年も前のことであり、『2016年の週刊文春』を過去の『週刊文春』を振り返るだけの本だと捉えてしまうのはあまりにもったいない。この本は、暇なときにねとらぼとか東洋経済オンラインを見た流れで文春オンラインの記事もちょくちょくスマホで読んでいたりするあなたに向けて書かれているのだ。
なぜ「週刊文春」は強いのか?
それにしても、なぜ『週刊文春』はここまでスクープを連発できているのだろうか。ちょっといくらなんでも強すぎないだろうか。
優秀な人材を数多く抱えているから? 取材のために予算を惜しまないから?
文春の強さの要因として頻繁に挙げられるこれらの理由もまあその通りなのだろうが、最も「文春」の強さの核心に迫っているのではないかと思えるのは、新谷学と藤原ヒロシとの対談での次のような発言である。
新谷 昨年、東京高検検事長だった黒川弘務さんが、朝日や産経の記者と賭け麻雀をやっていたことを『文春』がスクープしましたが、その後朝日新聞社の『月刊Journalism』という雑誌が、どうすれば私たちは信頼を回復できますか?とインタビューしに来たんです。
そこで私が強調したのは、賭け麻雀や取材源との距離の近さが問題なんじゃない。ディープなネタを取ったのに書かないことが問題なんだと。優先すべきは記事を書くことで、人間関係を維持することじゃないんです。その覚悟を持てるか持てないかが、プロかアマチュアかの違いなんだと。
(最強の免罪符?NO FUTURE?|藤原ヒロシvs『週刊文春』新谷学・白熱対談(後編)より)
「やろうと思えば俺にだってできる」、そういうことを言う人はたくさんいる。しかし、それを言った時点で実際にやって結果を出した人とは圧倒的に差がついている。それでもやろうと思えばできるんだから、そういう人たちは往々にして自分の振る舞いを改めない。なぜならやればできるのだから。
黒川元検事長とここまで密な関係を築いていたのだから、きっと同じ卓を囲んだ朝日や産経の記者たちはきっと文春以上にとんでもないネタだって知ってはいたのだろうし、その気になれば文春のスクープ以上の記事だって書けるつもりでいたのではないかと思う。しかし、彼らはそれをしなかった。
新谷はさらにこう続ける。
私だったら記者を麻雀に行かせて、「黒川検事長独占告白5時間」って、全部書きますよ。朝日新聞も社長直轄で、部署の垣根を超えた精鋭部隊をつくって、政権の調査報道を1年間地道にやり続ければ、風景が変わるのではないかと。
(「最強の免罪符?NO FUTURE?|藤原ヒロシvs『週刊文春』新谷学・白熱対談(後編)より)
勝負あり、だろう。
結局のところ、どれほど強力な取材元との関係を築こうとも、朝日や産経の記者は書こうと思えば書けたはずのスクープを書こうとはしなかったし、スクープというものが報道メディアにとっていかに重要であるかを本質的には理解しようとはしなかったということなのではないか。
現在、新聞や雑誌、ありとあらゆる紙を中心とする媒体が陥っているジワジワとした衰退局面を打破するためには、興味を持っていない人すらも振り向かせる強力なスクープ、すなわち強力なコンテンツを発信し続けるということができなければ、やがて死に至ることは明白であるにもかかわらずである。
そのような、当たり前といえばあまりに当たり前すぎることを、新谷学をはじめとする「週刊文春」を送り出す人々は、真に理解し、それを実行しようとしているからこそ、週刊文春は徹底してスクープを追い続けるし、どの雑誌、どの新聞よりも強力な「メディア」として否応なく視界に入ってきてしまう存在感を放つことができているのだろう。
現代は、スマートフォンやSNSの普及によって、手軽に情報発信を行うことができる、誰しもが「メディア」になれる時代である。そんな時代だからこそ、柳澤健の各著作、そして恐らくは彼の代表作と呼ばれるであろう『2016年の週刊文春』は多くの人に読まれるべき一冊である。取りあえずねとらぼスタッフは全員これ読むべき。
おまけ:柳澤健のオススメ本2冊
『1976年のアントニオ猪木』
アントニオ猪木が1976年に行った3つのリアルファイトを通して、アントニオ猪木がいかにプロレスラーとして傑出かつ異常な存在であったのかを明らかにする柳澤健の処女作にしていまだ最高傑作に推す人も多いであろう一冊。本作のハイライトであるモハメド・アリ戦のくだりも素晴らしいが、その手前で語られる猪木とリアルファイトではなく、最高のプロレスをした柔道のオリンピック金メダリストであるウィリアム・ルスカの章がプロレスラーと格闘家の違いというものをしみじみと考えさせられ最高。
『2011年の棚橋弘至と中邑真輔』
あまりに偉大すぎる創始者アントニオ猪木の呪縛と総合格闘技という黒船の到来によって、かつてない危機にひんした新日本プロレスを支えた2人の中心選手、棚橋弘至と中邑真輔のあまりに長い苦闘と再生の軌跡をたどる。正直その辺のビジネス書の100倍くらい勉強になると思っている。あまりに強力すぎる先輩の存在や、強すぎる外資系ライバル会社に苦しむサラリーマンにオススメ。個人的に、とっくに過ぎ去った過去となっていた日本のゲーム業界の黄金期や洋ゲーの台頭に散々悩み苦しめられた自分のゲーム業界での経験と重ねてしまい、何度読んでも泣きそうになる。