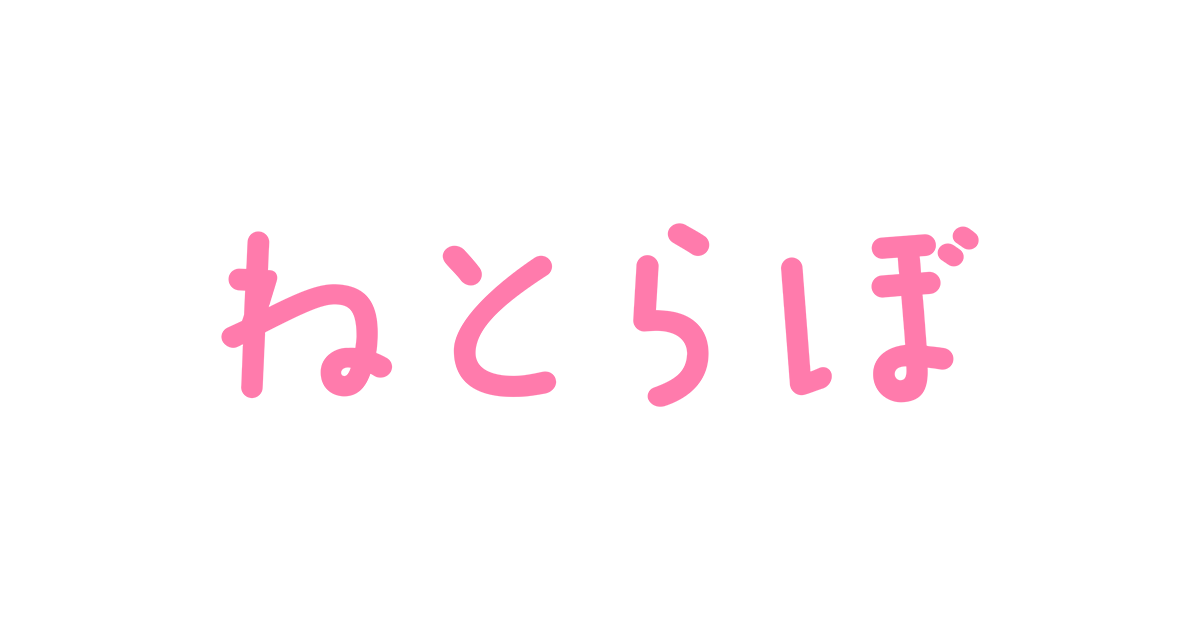萩尾望都が日本のマンガの全歴史のなかでも最も傑出した短編作家の一人であることは論を待たない。
ときに少女マンガの最高傑作とまで称えられる、かの『ポーの一族』は連作短編で成り立っているし、『11人いる!』や『エッグ・スタンド』のような凄まじい作品も数知れない。
何より、からだが腰で繋がった双子の少女の語り尽くしようもない想いを、わずか16ページで描き抜いた『半神』は、いまなお伝説的に語られる一作だ。萩尾作品のなかから歴史に残る優れた中短編を選び出そうとすれば、両手の指があっても足りないことだろう。
今回、わたしはその数ある名品のなかから、バレエものの短編集『青い鳥』の名を挙げたい。その理由は、前回の記事で藤田和日郎『スプリンガルド』を選んだときと同じで、単にこの作品が好きなのだ。

ライター:海燕

ジャンル横断エンタメライター。主にマンガ・アニメ・ゲーム・映画を題材に、読者が感じる違和感や評価の分かれ目を言葉にする記事を執筆。最近の仕事は『このマンガがすごい!2025』CLAMP特集、マルハン東日本「ヲトナ基地」連載など。
X:@kaien
note:@kaien
「けれどもほんとうのさいわいは一体何だろう。」
べつだん、これが『半神』のような奇跡的なマスターピースだというつもりはない。萩尾の無数の名作傑作のなかでは、むしろ地味な、とくべつ目立たない一作であるかもしれない。
だが、わたしは他の珠玉の作品群と比べても、どういうわけかこのさりげない作品が好きだ。
この1冊に収められた4つの短編の冒頭を飾る「青い鳥 -ブルーバード-」の物語は、わたしが「しあわせ」というあいまいな概念を考えるとき、真っ先に思い浮かぶ作品でありつづけている。
いったい、ひとはどうすればしあわせになれるのだろう。そもそも、しあわせをめざすとはどういうことなのだろうか。宮沢賢治『銀河鉄道の夜』の「けれどもほんとうのさいわいは一体何だろう。」 というセリフではないが、しあわせというものの輪郭はいかにも茫漠としている。まるで、近づけば近づくほど遠のいてゆく儚い蜃気楼か何かであるかのように。
「青い鳥」の登場人物たちも、そんなしあわせというものの幻影性に惑わされ悩み、苦しむ。これは、バレエというアートを通して、人間の最も深いところをえぐり出した一作なのだ。
あるいは、このマンガを読む前と読んだ後では、しあわせに対する考え方が根本から違ってしまうかもしれない。無邪気に自分はそれなりにしあわせだと思い込むことはできなくなるかもしれない。
萩尾望都が読者ののど元に突きつけるナイフの切っ先は、そんな危険な鋭さを備えている。それでもかまわない、むしろそんな作品こそ読んでみたいという人に読んでいただきたいマンガである。
青い鳥はいつか飛び去る
「青い鳥」の物語は、22歳のバレエダンサー・アシュアが所属するバレエ団に、天才的な新人ヤン・ラファティがやってくるところから始まる。その内気で人見知りする性格とはうらはらに、若くはつらつとして「青い鳥」を踊るヤンは、アシュアの恋人をも奪い去る。
一座の注目を集め、アシュアに対抗するかに見えるヤンに対し、アシュアは嫉妬を隠せなくなっていく。
「青い鳥」は中期萩尾望都の作品だけあって、綺麗ごとでは済まない深い人間理解を感じさせる作品だ。主人公であるアシュアにしてからが、ひとりの人間として完璧にはほど遠い性格である。
かれは、優れたバレエダンサーであるばかりか、嘘を吐いてまで、まわりの評価を高めていく(ように見える)ヤンに向かって激しい焦りと対抗心を抱くのだが、その様子は少しコミカルではあるもののリアルで、決して笑い飛ばして済ませられるものではない。
貧しく無名なバレエ団のなかで、しだいにヤンは「幸運を呼び込む青い鳥」と呼ばれるようになり、賞賛と喝采を集めてゆく。しかし、ヤン本人はなぜかアシュアを気にするようでもあり――と、ストーリーは続き、「嘘つき」のヤンが秘めていた秘密が明かされるとともに終わる。
そのとき、読者は「しあわせ」というものがはらむ二重の意味を知ることだろう。つまり、この短編のテーマは「幸福」であると同時に「幸福の不可能性」なのである。
ひとは何かを手に入れ、その甘さを味わっているとき、しあわせだと思う。しかし、そういった幸福は決して永続的に続くものではない。いつかは必ず「青い鳥」はその人から去っていくことになる。
その意味で、理想的な幸福とは絶対に達成不可能な目標なのだ。だが、それでもひとは幸福の青い鳥を探さずにはいられない。まるで、それを手に入れさえすれば、いつまでもしあわせに暮らすことができると信じ込んでいるかのように――。
「青い鳥」の結末は、いくらかシニカルではあるが、単なる皮肉に留まるものではない。しあわせの青い鳥は、いっとき近寄って来たかと思っても、いつもそのひとのもとから飛び去ってゆく。それでは、ひとがその鳥を求める意味とは何なのか? しあわせとは単なる夢みがちな人間たちが垣間見る幻想に過ぎないのか? それがこの作品のテーマである。
物語のクライマックス、ひとが決して獲得できないはずの「永遠」が示唆され、人々の短い幸福と対比されるとき、すべての読者は自分自身を省みずにはいられないことだろう。まさに秀作というほかない優れた短編である。
永遠はここにある
『青い鳥』には「青い鳥」のほか、「ロットバルト」など3つの短編が収録されている(ちなみに、文庫版『ローマへの道』には「青い鳥」と「ロットバルト」に加えて中編「ローマへの道」が入っている)。
「ロットバルト」は、とあるバレエ団にやって来て悪魔ロットバルト役を務める寡黙な男を主人公としたミステリーだ。その男があらわれるとともに、バレエ団のスターは死亡し、疑惑はかつて彼女の恋人だったかれに向けられる。
ほんとうにかれが元恋人を殺害したのか? もしそうでないとしたら犯人はだれなのか? 短いページのなかでついに真相が明かされるまで状況は二転三転し、読者の興味を逸らさない。その後には、ちょっとコミカルな結末が待っている。
萩尾望都の作品にはめずらしく、スウィートなハッピーエンドの恋愛ものといえなくもない。それこそ『半神』のような神がかった傑作ももちろん素晴らしいが、こういったわりあいノーマルな短編を描かせてもこの作家はほんとうに上手いと思わせられる。
くりかえすが、「青い鳥」や「ロットバルト」は天才作家・萩尾望都の最高傑作と呼べるものではないだろう。いずれも十分すぎるほどに優れたマンガではあるが、この作家はあまりにも頂点が高すぎる。
しかし、ぼくはたとえば『トーマの心臓』や『残酷な神が支配する』といった人間心理のくらやみの底をえぐり出すような長編と比べても、こういったビターでスウィートな短編が好きなのだ。
ここで描かれているものは、あえて言ってしまうのなら、わりあいどこにでもいるような、平凡といってもいいような人間たちの姿である。しかし、そういった凡庸な人々の描写を通して、萩尾の観察力は人間性の普遍の真実といったところまで到達してしまう。
「青い鳥」のセリフのなかにあるように、「なにもかもなくしても 希望がなくても 世界が不条理でも」、それでもなお残るもの、それこそが芸術の真髄なのだ。
そして、萩尾の筆はまさにその凄みを思い知らせる。「青い鳥」や「ロットバルト」を通して、読者はひとにしあわせをもたらすという青い鳥が、ほんのいっとき、自分のもとに飛んで来てくれたことを知るだろう。
その鳥はかならず、すぐその人の元から去っていく。だが、ふたたび本のページをひらけば、その鳥は不思議とそこにいてくれる。永遠はここにある。不世出の少女マンガ家である萩尾望都の本をひらくとき、わたしたちはいつでもその神秘な指さきにふれることが叶うのである。