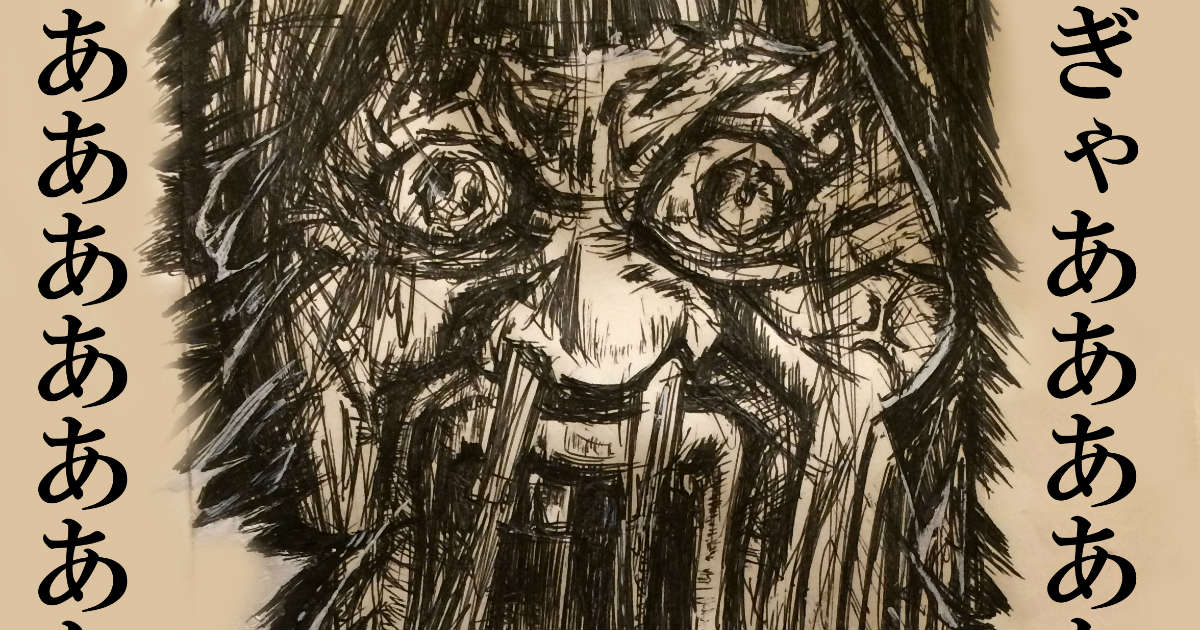作家志望者が作家死亡者にならないために。
INDEX
- 1 自戒を籠めて記す
- 2 10年に一度のチャンスが事故物件
- 3 「大物A」の自伝を書いてほしい。「絶対に売れます」(編集談)
- 4 凄腕を自称する編集者の下劣な一言
- 5 クリエイターが早めにしなければならない契約の話
- 6 編同士は自伝と称して、結託して「売れる自己啓発書」にしようと無断で企んでいた
- 7 私、文章がド下手なんですよ――そう自称する編集者が、作家の文章を全赤入れする怪奇現象
- 8 新たなモンスター登場――編集Δさんの意見が企画立ち上げ人の意見と真逆で対立。毎回ひっくり返される
- 9 仲介役に実権はない。版元の出版社が絶対
- 10 こういう人間が年収2000万超えの社会
- 11 作家志望者が作家死亡者にならないための教訓
- 12 最後に残ったもの
- 作者プロフィール
- 関連キーワード

1 自戒を籠めて記す
これから記す内容は、絶対に口外すまいと思っていた。
自分の不甲斐なさに凄まじい徒労を感じるし、思い出すだけで吐き気がこみあげてくる。事実、僕の体重はこの3年間で10キロ減り、後頭部には、2センチ弱の円形脱毛症ができた。小説を書くという唯一の「武器」はボロボロにひしゃげ、弾丸の装填が不可能なほど錆び付いてしまった。
そんな敗残兵の物語を、誰が開示しようと思うだろう?
物事を理性的にとらえられる人間なら、この体験を物語にしようなどとは、思わないだろう。
だが、感情が理性を上回ることもある。
絶対に、許せないことがある。そして知ってほしいことがあるのだ。
あらかじめ断っておきたいのは、完全に個人的な感情から、この物語を綴ろうと思ったわけではない。自分の肉体とかどうでもいい。
そんな作家の端くれに起きた悲劇――或いは喜劇を、このまま告発しないでいることは、歪な構造に支配された業界全体、そして業界に搾取される側の人間たちにとって、本当に大切なものを失うことにつながってしまう。宝石のように貴重な若さを、石化させてしまう。そんな気がするのだ。
この物語を、すべてのクリエイターに捧げる。
2 10年に一度のチャンスが事故物件
想像してみてほしい。
いま、あなたの前には雪が降っている。
数年振りに見る雪である。その美しい光景にあなたは、何か、運命じみたものを感じている。秋葉原の喫茶店で、窓から流れる雪を見つめながら、あなたは、一本の電話を受け取る。
「Aです」
“大物A”は、突然、自分の名前を名乗った。
世界から音が消えた。
「きみの作品、読んだよ。……凄いね。正直、こういう言い方が正しいのかわからないけれど、脱帽した」
そんな言葉の断片が、遅れて鼓膜から入ってくる。目の前には雪が降っている。視界がチカチカ点滅する。外部から入ってくる予想外の情報を、脳が処理しきれずに、戸惑っているのだ。
なぜA? どうしてA? そんな大物が何で突然?
――それが、最初の疑問だった。Aさんと僕は、一切交遊がない。隣接する友人も、関係者もいない。正直テレビの煌びやかな世界でしかしらないのだ。
あらかじめ断っておくが、この件に、J田さんは一切関係がない。僕とAさんの関係は、一切表に露出していないから、誰も想像つかないだろう。Aさんは、正真正銘、世界的なアーティスト/作家である。
「会おうよ」
翌週、僕はAさんと会食した。
待ち合わせ場所は、渋谷だった。世界で活躍する人間が、渋谷の居酒屋にいる、ということに対して、僕は不思議な感慨を覚えた。世界って本当にセカイだったんだ。渋谷だったんだ。そんなことを漠然と直観したのを覚えている。
何を食べたのかは覚えていない。家族の話、創作の話、いまどこに住んでいるのかという話をしたように思う。握手をして別れた。
その時は、何の依頼かわからなかった。
このまま終われば、美談の一言で済ませられたのに。
3 「大物A」の自伝を書いてほしい。「絶対に売れます」(編集談)
美談――「美しい話の反対」は、翌日やって来た。
編集者を名乗る人間からのコンタクトだった。聞いたこともない名前だった。
「どもどもー! Aさんよりご紹介を受けました、凸凹(デコボコ)出版の×(ペケ)田ボツ男です」
無論、×田ボツ男は偽名である。
「あなたの作品を見ました。ぶっちゃけ衝撃的でした! 実は現在、Aさんのとある企画を進めていまして……しかし一向にAさんのOKが出ず……企画が難航して、困っていたんです。そんな時、あなたの原稿をAさんよりご紹介されまして……もう私の直観レーダーがね、ビンビン! 繊細な部分が刺激されて狂おしいほどビンビンです!」
どういうことですか?
「ここ10年で最も熱い人物の一人です。世界的な評価も高い。先日は、○○○○賞を受賞されました。ニュースでも見たでしょう? しかし、あれだけの実績を誇っているにもかかわらず、著作がない。やはりあれだけの方ですから、これまで何度も出版依頼はあったようなのです。だが、うまくいかなかった。作品に対するこだわりが異様に強く、そのあまりのこだわりの強さ故に、企画が倒れてしまうこともしばしばです。そんな人物ですから、私どもの企画に、なかなか首を縦に振らなかったのです」
僕は黙って聞いていた。初対面の人間は、信用しないタチである。
「なのに、あなたの作品には反応した。私はすぐに企画を某出版社に持っていきました。自社では取り扱えない規模の企画だったからです。難関で非常にハードルの高い編集部です。すると! なんと企画が一発で通ってしまったんです! 費用対効果が最も高く、広告を打ってくれて、出せばほとんどの作品がベストセラーとなるところに、なんと! 一発で通りました。これまで一度も通らなかった企画が、通ってしまった。宣伝費用で、2000万は使って貰えます。JRの中吊り広告あるでしょう? あそこに載せられそうです。これもすべてあなたのおかげです。あの、それで――来週お時間ありますか?」
4 凄腕を自称する編集者の下劣な一言
相手は、凄腕をやたらと自称する編集者だった。
これまで、ベストセラーを墓場に持ち込めないほど量産してきたらしい。
非正規雇用の、インセンティブ方式で報酬が発生する社員らしい。
ただ、彼が手掛けてきたのは、物語を構築するタイプの作品ではなく、
まったく、別のジャンルの書籍だった。
端的に言って、自己啓発書やビジネス書だった。
正直、ヘドが出るほど嫌いなジャンルである(というより、今回の一件以降、自己啓発書系の編集さんとは二度と関わりたくないと思った、という表現が正しい)。
ビジネス本――自分の過去の栄光を成功法として提示するようなアーティストは、すでに賞味期限切れの作家である、という見方は根強い。もちろん希有な例外はある。しかし基本的に――現在進行形でトップクラスの人気を有しているアーティストは、そういった依頼には、目もくれない。アーティストとして、致命的なダメージを受ける可能性すらある。そんなものを、本当に“大物A”がOKするのだろうか?
しかし、その編集者が結果を出していることも事実。小説とは、相容れない世界の編集であるけれど――しかし「編集者」であることに変わりはない。
(どんな人間だろう?)
そう思いながら、打ち合わせた仲介役の編集者、×(ペケ)さんとのやりとりは、行く末を暗示させるものだった。
ペケさんは、ギラついた目を光らせながら、開口一番、こういった。
「1週間で1000万です」
僕は念入りに珈琲をスプーンで掻き混ぜた。
「鏡さんは筆が速い。1週間もあればAさんの自伝を完成させられると思います。1000万近く見込める企画です。これは私の編集者としての勘ですが、統計的に弾き出した数字でもあります。絶対に売れる企画です」
さすがに大袈裟すぎると思ったし、1000万なんて、正直自分にとって、何の意味もなさない。こういうと怒られるかもしれないが、僕はもう、そういうのはいいのだ。いや、もちろん、金銭的な余裕は必要である。最低限の生活をするために、欠くことのできないものでもある。
でも、僕はもう生きたいとも思わなかった。
話を戻そう。
大物Aは、国際的な認知度が高いものの、これまできちんとした著作はほとんどない。世界的な賞を受賞したこともある。日本で誰も知らない者はいないはずなので、かなりの需要はあるはずだ。それは、客観的に、理解できた。かなり著作は売れるだろう。
「Aさんは、あなたが執筆者ならば、ぜひ自著をお願いしたいと申しております。無論、扱いは、あなたの単著での著作となります。これは自伝ですが、まったく新しい自伝です。ドキュメンタリー風味の小説なのです」
ドキュメンタリー風味の小説?
「ええ。あなたの小説です。間違いなく。インタビューを通じて、Aの生涯を聞き取り、それを物語化してもらいたいのです。それが、あなたならできる」
契約に関してはどうなりますか? と僕は尋ねた。